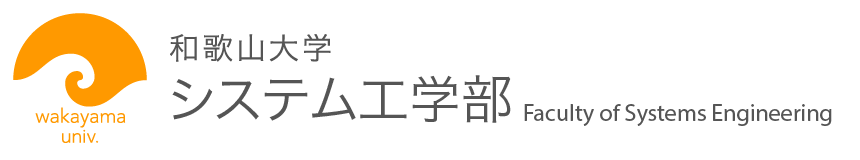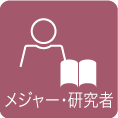複数の技術領域を見通し、複合的に専門を学ぶ
近年、科学技術の急速な発展に伴い、さまざまな工業技術が高度化・専門化してきました。また、一方で、エネルギー、環境、情報のように、複数の専門分野の成果を複合的・横断的に応用することが、新しい技術開発や地域産業の再生につながるようになってきました。つまり「高度な専門性」と「複数の技術領域を見通す力」の両方が求められているのです。
このような産業界や社会の要請に、より柔軟に対応できるように、システム工学部は、10のメジャーで構成される1つの学科、システム工学科としています。
システム工学部長挨拶

システム工学部長 中村 恭之
2025年度で30周年を迎えたこの学部では、これまで多くの優秀な人材を育て、研究成果を世界に発信してきました。
かねてよりシステム工学部は情報関連技術の教育に注力してきましたが、昨年度からは情報の基礎と応用技術を基盤とする高度な専門教育を提供するためカリキュラムを改善しました。これにより、情報技術を基にした新しい工学を学びたい学生にも、情報技術をさらに深く追求したい学生にも対応できる教育環境を整えています。また、本学部の特色である複合領域を学べるダブルメジャー制は維持しつつ,より高度な専門知識と技術を実践的に習得できるよう、博士前期課程の2年間までシームレスに学べる6年制も選択可能にしました。
これからもシステム工学部では、学生が自ら考え、実践する力を養える環境づくりに注力してまいります。地域との連携を強化し、社会で即戦力として活躍できるスキルを持った人材の育成に力を入れていく所存です。
教職員一丸となって、教育の質の向上と研究の発展に向けて取り組んでいきます。学生の皆さんには、挑戦を恐れずに自らの目標に向かって邁進していただければと思います。
沿革
| 平成7年4月 | システム工学部創設準備室の設置 |
|---|---|
| 平成7年10月 | システム工学部(情報通信システム学科、光メカトロニクス学科、精密物質学科、環境システム学科、デザイン情報学科の5学科)を設置 |
| 平成8年4月 | システム工学部 情報通信システム学科・光メカトロニクス学科・環境システム学科 学生受入開始 |
| 平成9年4月 | システム工学部 精密物質学科・デザイン情報学科 学生受入開始 |
| 平成9年8月 | システム工学部A棟竣工 |
| 平成11年5月 | システム工学部B棟竣工 |
| 平成12年4月 | 大学院システム工学研究科修士課程システム工学専攻を設置 |
| 平成14年4月 | 大学院システム工学研究科博士課程システム工学専攻を設置 |
| 平成16年4月 | 国立大学法人化 |
| 平成27年4月 | 5学科制から1学科10メジャー制へと再編 |