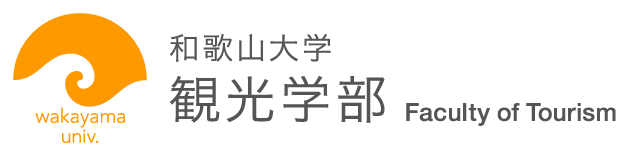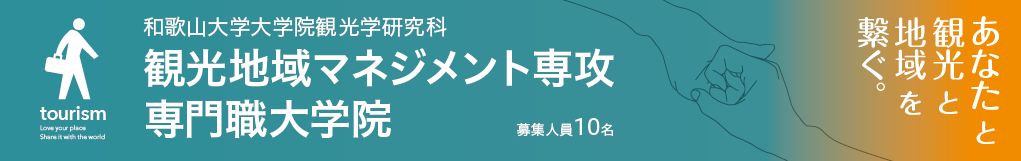和歌山大学観光学部長
大浦 由美
2000年代以降、観光および観光関連産業はめざましい成長を遂げ、経済の活性化や魅力的な空間創造の原動力として欠くことのできない存在となっています。その一方で、オーバーツーリズムに代表されるような諸矛盾が世界各地で顕在化し、持続可能な観光への転換が求められるようになりました。さらに、この間のCOVID-19の世界的流行は、国境や地域を越えた移動や対面でのサービスを前提とする観光に対して極めて深刻な打撃を与えることになりました。世界中でポストオーバーツーリズム時代、ポストコロナ時代を見据えた観光の回復と地域経済の立て直しが重要課題となっています。
現代を生きる私たちにとって観光は、単なる「楽しみのための旅行」を超えた重要な意義を持っています。例えばグリーンツーリズムは、農業体験や生産者との交流を通じて、食や農に関する問題を学び、農業という営みへの共感を育む機会ともなっています。また、その土地の風土が息づく祭事や暮らしのなかに、現代にも通じる知恵を再発見したり、戦争や災害の記録を通じて平和の尊さや歴史に学ぶことの大切さを心に刻むような経験をしたりするかもしれません。このように観光は、「日常」とは違った社会や文化に出会い、経験することを通じて、自己を見つめ直し、多様な社会への理解や他者への想像力を培う人間的成長の場でもあります。その点において観光は、平和で持続可能な社会の構築に欠かせない文化的営みであるといえます。
観光学は、いまや私たちをとりまく社会経済の基幹的領域を占めるようになった観光という現象を幅広く対象とする学問です。和歌山大学観光学部は、2007年に経済学部観光学科として、2008年からは国立大学唯一の観光学部としてスタートして以来、これからの観光をリードする高度な国際的・学際的視点を備えた創造的な観光人材の育成を目標として、観光教育研究における日本の、そしてアジアの拠点となることを目指してきました。
本学部では、多様な学問領域から成る教員が配置された観光経営、地域再生、観光文化の3つのコースを設置し、専門性を深めると同時に多角的な視野を身につけることを可能とするようなカリキュラム構成にしています。また、実践的な教育プログラムを数多く開設しているのも本学部の特徴のひとつであり、地域連携プログラム(LPP)や海外研修(GIP)など国内外の地域に多彩なフィールドを用意しています。英語で専門科目を学べるGlobal Program(GP2.0)も開設されており、アカデミックなコミュニケーション力を高め、世界で活躍できる観光人材を養成する環境が整っています。
このような教育プログラムの改善・充実にこれまで取り組んできた結果、2017年には国連世界観光機関(UNWTO)の観光教育認証である「tedQual認証」を、国内の大学として初めて取得しました。その後、2020年には大学院観光学研究科博士前期課程においても同認証を取得、学部については今日までに2度の更新を行い、教育プログラムのさらなる質向上に努めています。
観光学の特徴である幅広い学びの体系は、自分の未知なる可能性に出会うチャンスでもあります。基本となる科目をしっかり学んだ上で、これまでの得手不得手に囚われず、知的好奇心の赴くままに様々な学問領域にチャレンジして下さい。
これまでの観光のあり方そのものが根本的に問いなおされる時代にあって、この難しい課題に向き合い続けることは、私たち和歌山大学観光学部の社会的使命です。ともに学ぶ仲間と日々研鑽を積みながら、一緒により善い観光の未来を切り拓いていきましょう。皆さんの学びや成長を、私たち教職員は全力でサポートします。