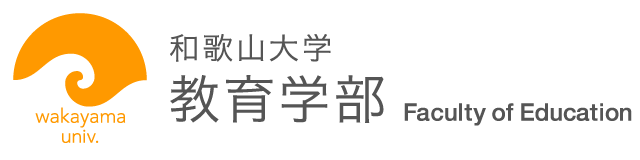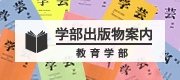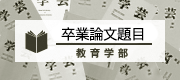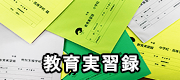学生の受入
受験者数と合格者数
|
2025年度(定員30人) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| コース |
志願者数 |
受験者数 |
合格者数 |
入学者数 |
入学定員 充足率 |
| 学校改善マネジメント | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| スペシャリスト | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 特別支援教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
授業実践力向上 |
8 | 8 | 8 | 7 | |
|
計 |
20 | 20 | 20 |
19 |
0.63 |
進路状況
学校改善マネジメントコース
修了生の多くは、学校現場に戻り、研究主任等の役割に就いて大学院での学びを現場に還元している。
また管理職や指導主事となり活躍している修了生もいる。
| 管理職 |
県指導主事 |
市町村指導主事 |
|
| 2024年度修了生 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年度修了生 | 1 |
1 |
1 |
| 2022年度修了生 | 0 | 1 | 1 |
| 2021年度修了生 | 3 | 1 | 2 |
| 2020年度修了生 | 1 | 2 | 2 |
| 2019年度修了生 | 3 | 1 | 1 |
| 2018年度修了生 | 6 | 0 | 0 |
| 2017年度修了生 | 3 | 3 | 0 |
(2025年5月現在)
授業実践力向上コース
学部卒院生の多くは、修了後、学校現場で教員として活躍している。2024年度修了生の教員就職率は約80%である(講師も含む)。
教員就職をしていない者は、追加で教職員免許状を取得するため、さらに学習を進めている。
進路先データはこちらのページへ
修了生のコメント
授業実践力向上コース(2021年度修了生)
 石橋新菜さん(和歌山市立高積中学校教諭)
石橋新菜さん(和歌山市立高積中学校教諭)
1.大学院に行こうと思った理由
私は大学卒業を目前にしたとき自分に自信が持てず、現場に出るまでにもっと力をつけたいという思いがありました。そんな時、和歌山大学教職大学院のパンフレットを目にし、様々な校種の仲間とのかかわりが持てることや、現場に出ている先生方と同じ授業の中で学びあえるということを知り、この環境の中で学んでみたい!と思い教職大学院に進学しました。
2.大学院で一番印象に残った授業
教職大学院では、様々な校種の仲間や現場に出ている先生方と一緒に学びあう機会が多く、大学時代には経験できなかったような多方面からの学びがたくさんありました。何より印象に残っているのは、週1回のインターンシップ実習や小規模校実習です。教職大学院で学んだことを実際の実習で生かし、振り返ることができたためとても自分の成長を実感できました。初めは授業に対する不安が大きかったのですが、子どもたちとの反応や意見に触れていくうちに、「もっと子どもたちが必死になるような楽しい授業を作りたい!」と思うようになりました。常に子どもたちの目線に立って考えるという意識をこれらの実習で培うことができたと思います。
3.大学院の学びで、今役に立っていると思うこと
教科のことはもちろんですが、生徒指導や学級経営、生徒理解など学校現場に出るために必要不可欠なことを学ぶことができました。 初めて現場に出た際には周りの先生方から「生徒との距離感が上手」「落ち着いて対応できている」と言っていただけることもあり、教職大学院での経験が力になっているなと実感することができました。自分が意識していない、無意識の行動にも教職大学院での学びが役に立っているのだと思います。
4.後輩へのアドバイス
教職大学院での生活を通して学んだ「どんなことに対しても常に学び続ける」という姿勢が今の私を支えてくれています。皆さんも何かに迷ったら、自分を信じて挑戦してみてほしいと思います。きっと何かの形で自分の力になるはずです。
スペシャリストコース(2022年度修了生)
 塩地文哉さん(田辺市立会津小学校教諭)
塩地文哉さん(田辺市立会津小学校教諭)
1.大学院に行こうと思った理由
教員になって10年が経ち,私は「学び直したい」という気持ちを強く持っていました。特に,体育科に興味があり,その専門的な知識を身に付けたいと考えていました。しかし,日々教員として働きながら,そのような知識を身に付けるためのまとまった時間を確保することは難しかったです。そこで,思い切って教職大学院に進み,学ぶための時間をしっかり取ろうと考え,和歌山大学教職大学院に進学しました。
2.大学院で一番印象に残った授業
私が一番印象に残っているのは,「和歌山における家庭・地域と連携した学校づくり」という授業です。その授業の最後に,グループで総合的な学習の時間のカリキュラムデザインを行ったことが一番楽しかったです。私のグループは,和歌山市の教員,和歌山市出身の学生,県外出身の学生,紀南の教員の私という,バラエティに富んだメンバー構成でした。カリキュラムをつくる過程で,メンバーの多様な見方・考え方に触れることができ,「いい経験だなあ,おもしろいなあ」と思いながら活動したことが今でも心に残っています。
3.大学院の学びで、今役に立っていると思うこと
大学院の学びで,今,最も役に立っていることは,学校の取り組みの成果を,根拠のあるデータで示すことの重要性に気づけたことです。大学院に行くまでは,学校で取り組んだことの成果を,「やってみていい感じでした」程度でしか示せていませんでした。大学院で修了研究に取り組み,教授の皆さんにご指導いただいたことを通して,成果の測定方法を考え,データを集め,分析することの大切さを学ぶことができました。教職大学院を修了した今もそれらを意識して,取り組みの成果などを他の教員や保護者に説明することができています。
4.後輩へのアドバイス
和歌山大学教職大学院では,同期の院生や教授の皆さんと対話したり,大学図書館(特に書庫)を活用したりすることで,自分の学びをどんどん進めていくことができます。学び直しのための環境がしっかり整っているので,ぜひ教職大学院への進学を検討してみてください。
学校改善マネジメントコース(2022年度修了生)
 和田慎也さん(和歌山市立貴志南小学校教諭)
和田慎也さん(和歌山市立貴志南小学校教諭)
1.大学院に行こうと思った理由
私は若い時から、いろいろな先生方にお世話になりながら教員をやってきました。その自分が中堅になって、学校の運営に携わるようになった時に力不足だなと思うことや、お世話になった先生方に近づけているだろうかと考えるようになりました。自分がやってきたことや考えたことを、若手教員に語れるようになりたい、もう少し成長したいと思って大学院を受験しました。また、大学院に行った経験がある先輩やお世話になった元校長先生が大学院の教員だったことで、お話を聞かせてもらっていたこともあり、一歩踏み出せたと感じています。
2.大学院で一番印象に残った授業
大学院で学んだことで、「視野が広がったこと」が最も大きな成長だと感じています。毎週のインターンシップ、「学校安全と危機管理」の授業、福祉関係等の外部機関との連携に関わる授業など、学校現場で仕事に追われていたら後回しにしたり、おろそかになりがちな部分の知識や情報を習得し、補えたと思います。特にインターンシップで毎週月曜日に現任校に戻ることで、学校を客観的かつ俯瞰的に見ることができ、他の先生方の頑張りが見えたことも、大きな発見でした。
1年間の研究の成果を現任校で報告させていただいた時に、皆で研究に取り組めたことで見られた子供の変化や成長を伝えられたので、現任校の先生方にも頑張ってよかったなという実感を持ってもらえたのではないかと思います。自分より少し経験年数が下の先生方も主任を担うようになってきて、まだまだ教えてほしいけどより若い先生を引っ張らないといけない、どうやって頑張っていったらいいのか、と感じていたように思いますが、その先生方に「この方向性でやっていこう」と示せたのかなと感じました。
3.大学院の学びで、今役に立っていると思うこと
視野が広がったことで、授業をつくる際にも、校務分掌を担う際にも、より客観的に考えることができるようになっていると思います。大学院に行くまでは、子供のために良いと思うことなら何でもしなければいけないと考える傾向にありましたが、現在は、学校全体を見渡して必要やリソースに応じて取捨選択しないといけないと思えるようになりました。何のためにするのか、どういう価値があるのか、効果はどうかといった多角的な視点で現場を見えるようになったと思います。
この多角的な視点は、大学院で出会った仲間によって得られました。和歌山県内の他の地域から来ている院生や、幅広い年代の院生がいたことで、大学院生活がとても楽しかったし、いろいろな刺激が得られました。自分が当たり前と思っていたことが、実は当たり前じゃないと気づくこともありました。働き方や、行事の持ち方、地域との連携のあり方など、地域によって多様性があることが知れて、しなければいけないと思っていたことがしなくても良いと思えたので、学校での実践を見直すきっかけになっていると思います。
4.後輩へのアドバイス
2年目に現場に戻って、実践しながら研究を行うので、学校の先生方の協力を得られないと苦労すると思います。1年目のインターンシップの時間に、2年目を見通して、多くの先生たちとコミュニケーションをとり、時には悩み相談に乗るなど、管理職も含めて先生方との関係づくりをしっかりしておいた方がいいと思いました。私もインターンシップでは、放課後の研究授業の指導案検討に入って一緒に話をしたり、授業の補講に入った学級で担任と話したりと、関係づくりを意識しながら過ごしていました。インターンシップを始め大学院での学びは、現場を離れて、客観的・俯瞰的に現場や実践を見直すには非常にいい機会なので、ぜひ、有意義に過ごして欲しいと思います。