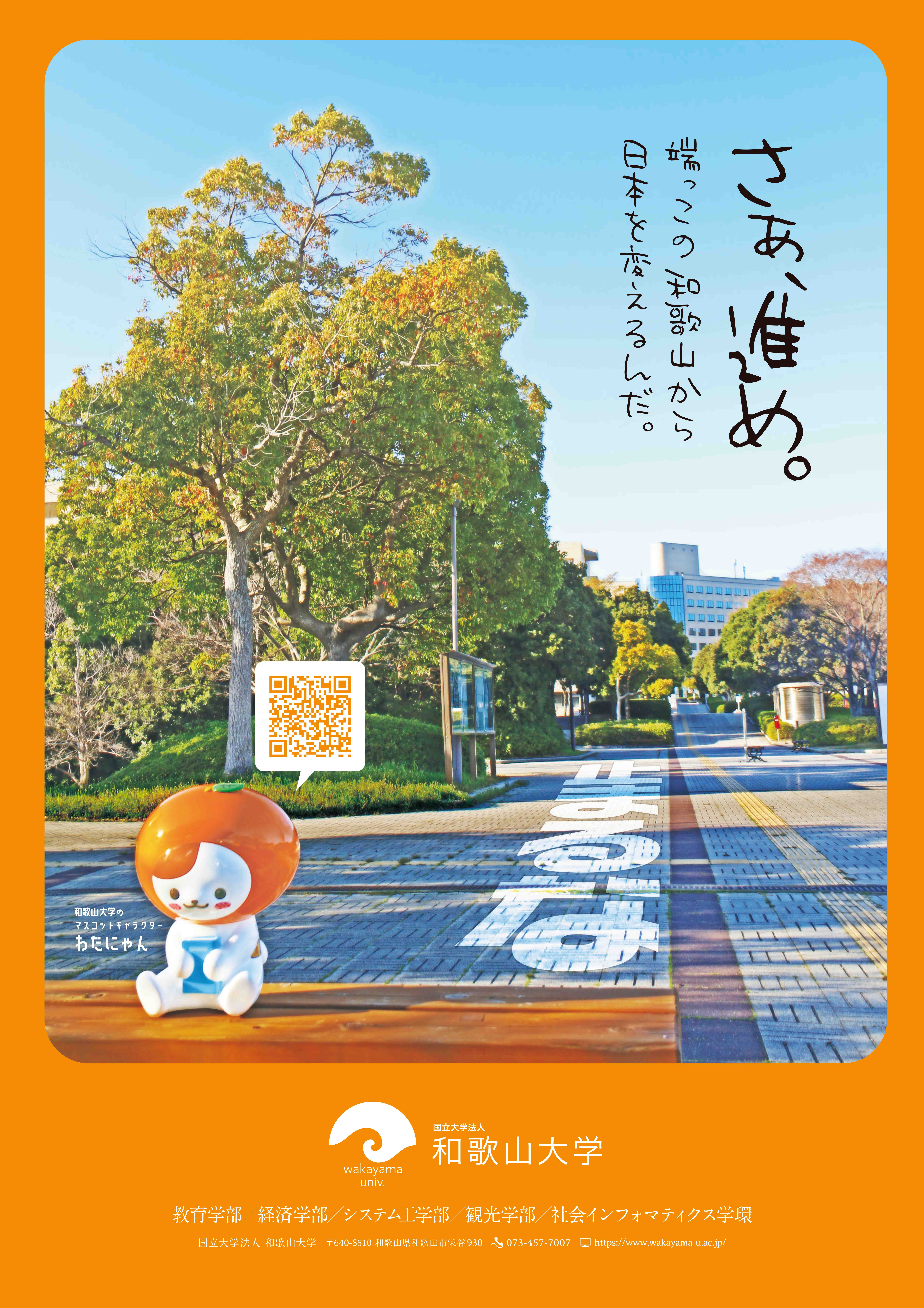大学紹介
広報・情報公開ギャラリー
広報ギャラリー
大学案内
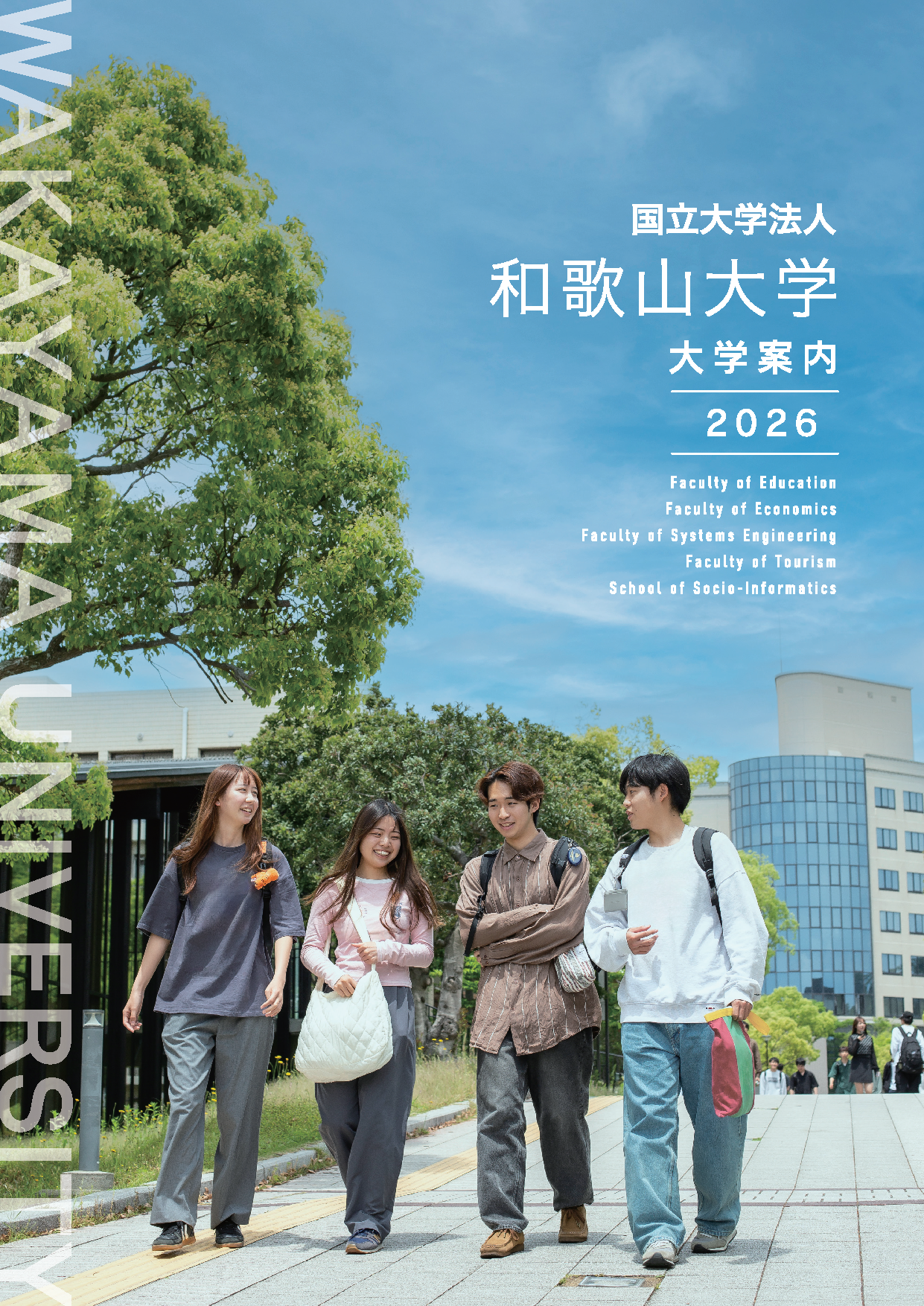
和歌山大学概要
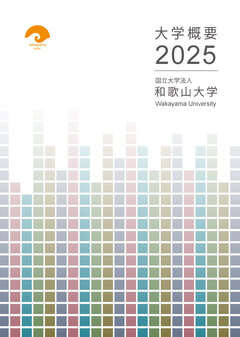
研究者紹介冊子<和歌山大学解体新書>
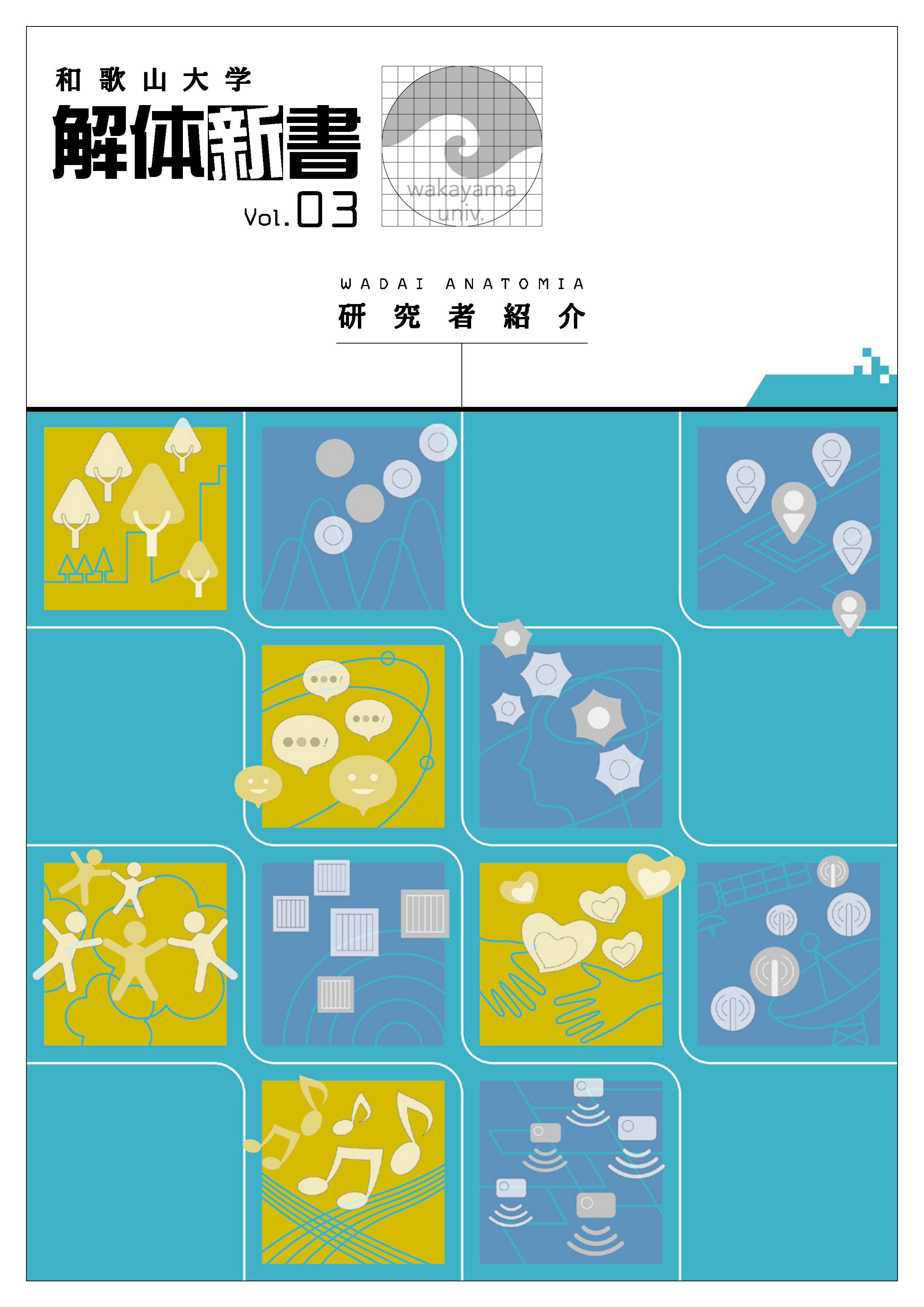
大学公式SNS
広報ポスター
情報公開ギャラリー一覧
教育情報の公表
独立行政法人等情報公開法第22条に規定する情報を掲載しています。
その他情報公開アーカイブ
- 戦略情報室 分野別レポート
- 大学概要HTML版(役職員、機構図、学部センター等の各種データはこちらから)
- 和歌山大学(栄谷キャンパス)の電力使用状況
- その他公開情報
About
大学紹介
- 目的及び使命
- 学長メッセージ
- 学長室だより
-
- 組織
- 業務
- 財務
- 評価・監査に関する情報
- 大学等の設置に係る設置計画書及び設置計画履行状況報告書等に関する情報
- 学長選考
- 役職員の給与水準情報
- 役員兼業の状況について
- 独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況等について
- 第4期中期⽬標・中期計画期間末に⽬指す専任教員の年齢構成
- 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
- 公益通報に関する通報・相談窓口について
- 情報公開・個人情報保護
- 和歌山大学における人権に関する基本理念
- 独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況等について
- 和歌山大学男女共同参画基本方針
- 和歌山大学におけるSOGIの多様性に関する基本方針及び対応ガイドランについて
- 国立大学法人和歌山大学情報セキュリティ基本方針(102KB)
- 国立大学法人和歌山大学における反社会的勢力に対する基本方針
- 公正な研究活動
- ハラスメント防止のために
- 和歌山大学教育ビジョン
- 教育情報の公表
- 学修成果の公表
- 教育の質保証 e-annual report他
- 高等教育の修学支援新制度
- 懲戒処分の公表について
- 調達情報
- 環境管理について
- 施設整備計画について
- 国立大学法人和歌山大学における禁煙の取り組み
- 国立大学法人ガバナンス・コードに係る適合状況等に関する報告書
- 女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針に基づくスケジュールの公表について(57KB)
- 和歌山大学 ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進宣言(69KB)
- 修学支援事業基金等に関する公開情報
- 広報・情報公開ギャラリー
- 交通アクセス
- キャンパスマップ
- 学部・センター等所在地連絡先一覧